アサギマダラの特徴や生態・について紹介!!

アサギマダラはとても綺麗な蝶で、幼虫もすごい見た目をしています。見た目が綺麗な蝶で、長い距離を飛ぶことができることで良く知られている蝶です。今回の記事ではアサギマダラの特徴や生態について紹介します。
アサギマダラは長距離を移動するので、旅をする蝶とも呼ばれています。暖かくなると北上して、寒くなってくると南下します。
渡り鳥のように季節によって集団で移動するとても不思議な蝶です。見た目もとても鮮やかなので、とても人気のある蝶です。
今回の記事では、そんなアサギマダラの特徴や生態について紹介するので、興味がある方はぜひ読んでみてください。
アサギマダラの特徴
アサギマダラは青白い模様が入っているとても綺麗な蝶です。模様部分は半透明になっていて日に当たると透けているのがわかります。
羽の他に胴体にもまだら模様があります。綺麗なアサギ色と特徴のあるまだら模様が名前の由来になっています。
他の蝶は羽に鱗粉がついていますが、アサギマダラの鱗粉はとても少ないです。
とても綺麗な蝶で、東京など都市部でも見かけることがあります。暖かくなると東京などの公園でも見かけることができますが、秋になって気温が下がってくると南下して暖かい場所に移動してしまうので、見かけなくなります。
アサギマダラの幼虫について

成虫はとても綺麗な模様をしていて、綺麗な蝶ですが、幼虫はものすごい体色をしています。
アサギマダラの幼虫は黒地に大きな黄色い水玉模様と小さい白い水玉模様が並ぶとても派手な体色をしています。
成虫は寒くなるど暖かい方へ移動しますが、幼虫は移動することができないので、冬場でも東京などで見つけることができます。
アサギマダラの生態
最初にも少し紹介しましたが、アサギマダラの成虫は季節によって長距離を移動します。
本州から沖縄などまで移動することができ、2000キロも移動したことも確認されています。海を越えることもでき、日本国内だけでなく台湾や中国まで移動することもあるそうです。
アサギマダラは高い気温が苦手で21度前後が適温と言われています。なので、夏場暑くなると北上して涼しい場所に移動します。
平地でも見かけることができますが、涼しい場所が好きなので、山地で良く見かけることが多いです。北上したアサギマダラが集まる場所は富士山の中腹などが有名です。他にも八ヶ岳、高尾山などが有名です。
観察してみたい場合はそういった場所に行ってみるのもいいと思います。
アサギマダラの幼虫の生態について
アサギマダラの幼虫はキジュランなどのガガイモ科の植物の葉っぱを食べます。
幼虫が食べているガガイモ科の植物は毒性の強いアルカロイドが含まれています。毒性のある葉っぱを食べていることで、アサギマダラも毒を持つようになります。
人が触っても平気ですが、鳥などが食べると吐き出してしまいます。幼虫はとても鮮やかな体色をしていますが、これは警告色だと言われています。
アサギマダラの幼虫は小さいうちは葉っぱを丸く傷つけてから中心部分を食べます。
これはトレンチ行動と言われるもので、あらかじめ葉っぱを丸く傷つけておくことで、植物が出す防御物質をせき止めることができます。大きくなると普通に葉っぱを食べるようになります。
丸く穴の空いたガガイモ科の葉っぱを探すとアサギマダラの幼虫を見つけることができます。
アサギマダラの大移動について
アサギマダラは長距離移動することで知られていて、マーキング調査でどこまで移動しているのか調べられています。
アサギマダラは寒くなると移動するので、秋になると台湾や南西諸島まで移動することが知られています。
マーキング調査とは成虫の翅に捕獲した場所や生年月日、個体番号などを記入したのち蝶を逃して、再び捕獲された場所や日時によって何時間でどこまで移動したかを調べる方法です。
アサギマダラは寒くなると集団で南下することはわかっていますが、どこで冬越をしているのかやどこで寿命を迎えるのかなどはまだわかっていません。
アサギマダラは1000キロ以上移動することや、1日に200キロほど移動することがわかっています。
アサギマダラの幼虫が食べている草と成虫が吸っている蜜の両方に毒が含まれています。毒を含んだ食べ物を摂取することで、アサギマダラの体内に毒を溜めます。
この毒のおかげでアサギマダラは鳥などから食べられずに移動に専念ができると言われています。


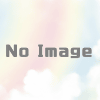
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません