カナブンとコガネムシは何が違う?特徴や見分け方について紹介!!

カナブンは夏になるとよく見かける昆虫で見かける機会の多い馴染み深い昆虫です。灯りに集まるので、ベランダや玄関などに集まってくることも多いです。昆虫採取に行くと見かけることの多い身近な昆虫です。今回の記事では、カナブンの特徴や見分け方について紹介します。
カナブンはキラキラと光っていて、メタリックな体色の特徴的な昆虫です。日本全国に生息していて、見かける機会の多い昆虫です。カナブンの幼虫は落ち葉や腐葉土の中に多く生息しているので、家庭菜園をしている方は幼虫を見かける機会も多いと思います。
カブトムシなどの昆虫採取に行くとカナブンを見かけることも多いです。子供がカナブンを捕まえて飼ってみたいと言われた方も多いと思います。
今回の記事では、カナブンの特徴や見分け方について紹介するので、興味がある方はぜひ読んでみてください。
カナブンの特徴

カナブンは丸い体をしていて、キラキラと光ってメタリックな体色をしています。体色は緑色っぽいものや褐色のものなど、個体によって違います。
日本全国に生息していて、見かける機会が多いので、子供のことに捕まえたことがある人も多いと思います。
カブトムシやクワガタを捕まえに行くと、カブトムシやクワガタと一緒に樹液を吸っていることが多いです。
大きさは3cm程度です。ずんぐりした体をしていて、見た目が可愛らしいので、勝ってみたい人も多いと思います。
飼育も簡単で、カブトムシやクワガタと同様の方法で飼育する事ができます。
カナブンの生態について
カナブンは夏に卵を地中に産み付けます。
卵から孵った幼虫は堆肥などの腐葉土を食べながら冬をこします。地中で越冬した幼虫はカブトムシなどと同様に土の中でサナギになり、夏になると羽化して地中から出てきます。
夏頃に活動を始めるので、成虫は6〜8月ぐらいの暖かい頃に見つける事ができます。
成虫になったカナブンは腐った果物やクヌギ、コナラなどの樹液を食べます。果樹園などでは落ちた果物に集まっている事がよくあります。昼間でも活発に活動しているので、昼に雑木林の中を探してみると簡単に見つける事ができます。
カナブンとコガネムシの見分け方
カナブンに似た昆虫にコガネムシという昆虫がいます。コガネムシは広葉樹の葉っぱを食べてしまい、コガネムシの幼虫は植物の根っこを食べてしまうので、家庭菜園をしている人には嫌われている害虫です。
その点カナブンは無害です。カナブンは腐った葉っぱや朽木を食べて分解してくるので、土壌を改良してくれます。
なので、カナブンを駆除する必要はありません。簡単にカナブンとコガネムシの見分け方を紹介します。
頭の形

カナブンとコガネムシでは頭の形が違います。カナブンは頭部が四角っぽくなっているのに対して、コガネムシは頭部が丸まっていて半円状になっています。
羽の付け根
カナブンは羽の付け根が綺麗に逆三角形になっているのに対して、コガネムシは羽の付け根が小さくて、丸っこい形をしています。
カナブンの仲間について
カナブンと一言に言っても日本には様々なカナブンの近縁種が生息しています。簡単にカナブンの近縁種を紹介します。
アオカナブン
青色の光沢が強いカナブンで、見た目が綺麗なので人気の種類です。涼しい場所が好きなので、北海道にも多く生息しています。
クロカナブン
名前の通り黒い体色が特徴のカナブンです。かなり生息数が減っているので、野生で見かけることはほとんどありません。
カナブンの飼育について

見た目が綺麗で可愛いので、飼育して見たいと思う人も多いと思います。カナブンはカブトムシと同様の方法で飼育することができます。
カブトムシの飼育キットで飼育することができるので、飼育は難しくなくとても簡単です。
餌も昆虫ゼリーを食べるので、餌で困ることもありません。飼育する場合は定期的にマットが乾燥しないように適度に霧吹きで加湿するようにしましょう。
カナブンの寿命はおよそ2年ほどです。カナブンは幼虫の状態で15ヶ月ほど過ごします。
成虫になってからは地上に出てからは9ヶ月ほど生きます。春頃に地中から出てきた成虫は越冬はせず、冬がくると死んでしまいます。


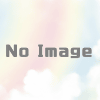
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません